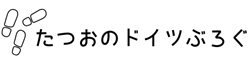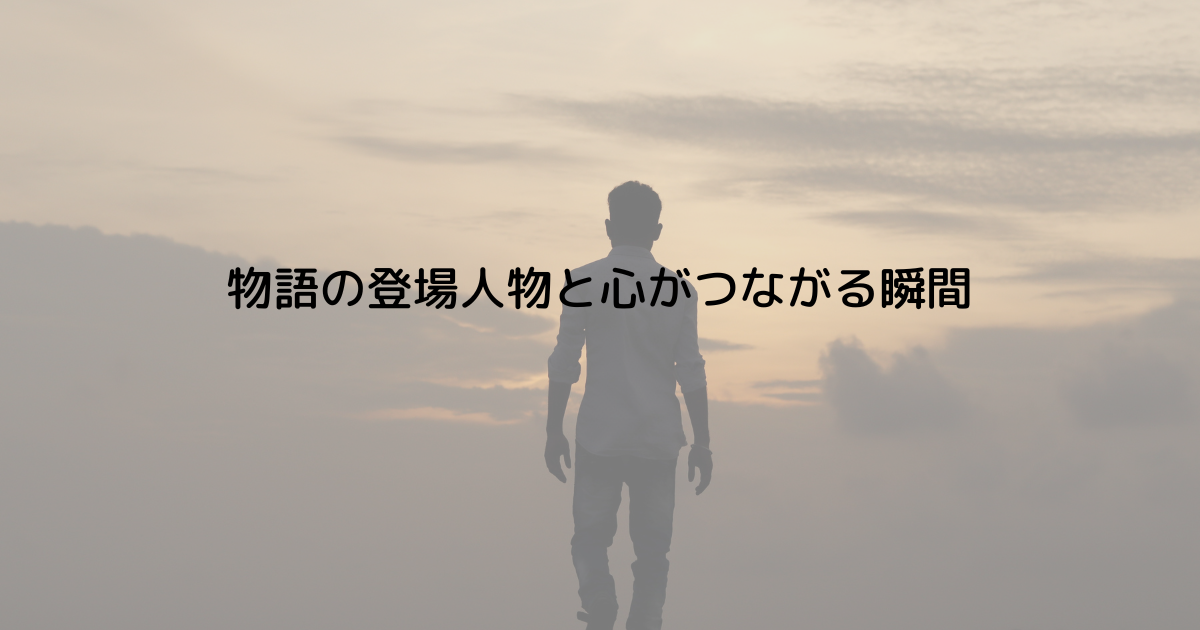だいぶ久しぶりの投稿になってしまった。
11月もすでに終盤で、来週からクリスマスマーケットが始まろうとしているライプツィヒである。
日中でも一桁台の気温の日が多く、”暗い冬”が
抜き足差し足で近づいてきている
のを感じる。
ドイツをはじめヨーロッパの寒い地域では、冬は
極端に日照時間が短くなる上、くもりや雨の日が
多い。それに加えて、ドイツでは寒色系の電球が極端に少なく、暖色系の電球が圧倒的に多い。
わたしは、日本のコンビニのあの人工的な神々しさが苦手だ。それにしても、暗い部屋が好まれるドイツでは暗くて見えないというのは日常茶飯事な気がする。
先日わたしの友人から欧州人と日本人の身体のつくりについて、おもしろいことを教えてもらった。どうやらこちらの人は、日本人に比べて目の色素が薄いようだ。
そのためわたしたち日本人よりもまぶさを感じやすいとか。だから、夏はみんなサングラスをする。
寒色系の電気が多い日本とはまるで逆なのだ。
ただ、暖色系の電気は暗いものの、寒色系より安らぎや落ち着きを感じられ、間接照明を部屋のあちこちに置けば、リラックス空間はあっという間に完成してしまう。
さらには、とてもムーディーな雰囲気が出て、わたしの楽しみといえば、好きなクラシック音楽をかけながら、じっとりとお酒を楽しむことだ。この時間は、1日の疲れを癒してくれる時間であり、わたしにとって欠かせない至福の時間である。
「ある男」に登場する悠人と心がつながる瞬間
さて、今回はまた本の感想回だ。平野啓一郎作「ある男」という作品を紹介したい。この作品に登場する「悠人」という少年に、ひどく共感してしまったのでそこから自分の体験も交えて紹介したいと思う。
この作品は一昨年映画にもなり、公開前から気になっていたわたしは、しっかり映画も観に行った。
原作を知っている状態で映画を観てしまうと、どうも内容が入ってこないと思うのはわたしだけだろうか。原作を読んでしまってから見る映画は、最低でも2回見なければその映画の良さが分からないのかもしれないと思った。
簡単なあらすじ紹介
300ページにも及ぶ作品だけに、ごくごく簡単にまずあらすじを紹介したいと思う。
殺人犯の息子として生まれた「ある男」は、そういう生い立ちから生まれつきの名前で生きることに非常に
”生きづらさ”を抱えていた。その後、ひょんな出会いから、男が強く望んでいた”ふつうの生活”は現実のものに
なる。「里枝」という同年代の女性と結婚し、一人娘の「花」を授かる。男は林業会社で働く日々を送る。
若手ながら、仕事に対する姿勢や生まれ持ったセンスの良さから、期待の新人だった。
だが、気の毒なことに山で仕事をしているときに命を落としてしまう。これはまだ、物語のほんの序盤であり、
ここから壮大なスケールで話は展開される。ある男と出会った里枝は、その前にも別の男性と結婚しており、
その際兄の「悠人」、弟の「遼」を授かる。だが、不幸にも弟の遼は生まれてから重い病を患い、ツラい闘病
期間を経て若くして亡くなる。さらには、里枝の祖父と立て続けに三人もの死を、母の里枝と息子の悠人は経験することになるのだ。
そして”ある男”の正体が、死後徐々に明らかになっていくようすが読者の好奇心を刺激する。
悠人の心に思いをはせる
身近なひとを3人立て続けに失うとはどんな心情だろうか。里枝は、思春期を迎えた悠人がどのような思いで
いるのか分からないでいる。思春期の息子というのは、いろんなことにセンシティブで、親と子の距離感も
難しい時期だ。ただ、物語の後半で一つの文学作品を通して、里枝は悠人のことが分かるようになってきた。
作中のなかに下記のような記述がある。
ともかく、彼女は、文学が息子にとって、救いになっているのだということを、初めて理解した。
それは、彼女が決して思いつくことも、助言してやることも出来なかった、彼が自分で見つけ
出した人生の困難の克服の方法だった。引用:本文 23 P.327 L16~18より
この作品の最後で、著作の平野さんはこのように語っている。
『ある男』の読後感を支える上で重要なのは、この少年、悠人だと思いました。読み終えたあとに
希望を感じるという意味では、不遇な境遇にいる子供が、自分の力で困難を克服しようとしていて、
周りもそれを見守る話にしたかったんです。
悠人は最終的に文学によって立ち直っていきますが、最初はそのような想定をしていませんでした。
自分と近すぎる話をかくのもどうか思いがちなのですし、作家が文学の素晴らしさを強調するのも
手前味噌かなと。
ただ、自分自身が十代のときにいろいろ思い悩んだ時、文学との出会いに救われたのはやはり大きな経験で、それは否定できないんですね。音楽やスポーツではなく、文学によって成長していく話を
書くべきだと、最終的には考えました。引用:【電子版特典】読者から寄せられた『ある男』の質問に答える
Q3.『ある男」の”希望”である悠人について より
悠人は若くしてもはや、自分のキャパを超えるような経験をせざるを得なかった。そしてそれは、彼に大きな心の傷をつくったことだろう。そんな苦悩のなか、文学に出会ったことで徐々にキズが癒え、
文学が心の友になったことは間違いないだろう。わたしはまさにこの部分に深く共感をし、悠人と心がつながったと感じた。
思い返してみると、わたしにとっても文学とは、生きる上で欠かせない存在だ。悠人と同じように、自分に
ぴったりの作品たちを読み漁っていた。10代という年代は、成長段階であるが故に血気多感な時期だ。それと同時に、いろんな影響を受けやすく繊細故にたくさん悩む時期でもある。だから、この人間形成期に触れるものは自分に大きな影響を与えるし、その後の自分の人生まで左右するかもしれない。すこしおおげさかもしれないが、この年代に経験したものが大きければ大きいほどそうではないだろうか。
文学の延長線上にある世界
わたしも10代の頃は、以前綴った『エミリの小さな包丁』のなかでおじいちゃんがエミリに対して放った言葉ではないが、自分の存在価値を他人からの評価で判断していたのだ。
「自分の存在価値と、自分の人生の価値は、他人に判断させちゃだめだよ」おじいちゃんは、いつにも増して渋い声で、ゆっくりと話した。「判断は必ず自分で下すことだ。他人の意見は参考程度にしておけばいい」
引用:『エミリの小さな包丁 第五章 失恋ハイタッチ サワラのマーマレード焼き』P.246 L6~7 より
わたしはいまだったらゲイであると自認しているため、それをなにも隠すことはないと思えるが、10代の頃はそれとは真逆だった。他人から受ける評価を、そのまま自分の評価として受け入れていたため、自分の性は「男性なのか女性なのか」ということがいつもの悩みだった。いわゆる”男らしくない”性格をしているため、それも悩みだったし、男らしくない性格を変えようと頑張った時期でもあった。別に悲劇のヒロインを演じているわけでは決してないのだが。そのときのわたしの救いだったのが、悠人や平野さんと同じく文学だったのだ。
そして文学はもちろんのこと、あの図書室という空間もまたわたしの救いになっていたことを思い出した。
中高と学校は違ったけれど、なぜか司書の先生と仲がよかったわたしは、お昼休みや長い休憩時間には足しげく通っていた。司書の先生は、普段授業を担当してくれる先生たちとはすこし距離があり、第三者てきな立場でたわいもない世間話に花を咲かしていたのを思い出した。
さいごに
わたしにとって文学は、自分の心に安らぎや平穏を取り戻してくれる”栄養剤”であるのと同時に、だれも自分を
否定してくる悪者はおらず、完全に自分の心をオープンにしてくれる存在だ。それは、司書の先生や図書室という
あの空間もまさにそう。悠人の話からだいぶ逸脱してしまったかもしれないが、そんな存在であり続ける文学を
”心のパートナー”としていつまでも愛したいと思うところである。
今日も最後まで読んでくれてありがとう。
ご質問、ご感想随時受け付けています。
下記リンクからお問い合わせページへ飛べます。
それではまた、次回の投稿もお楽しみに。