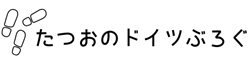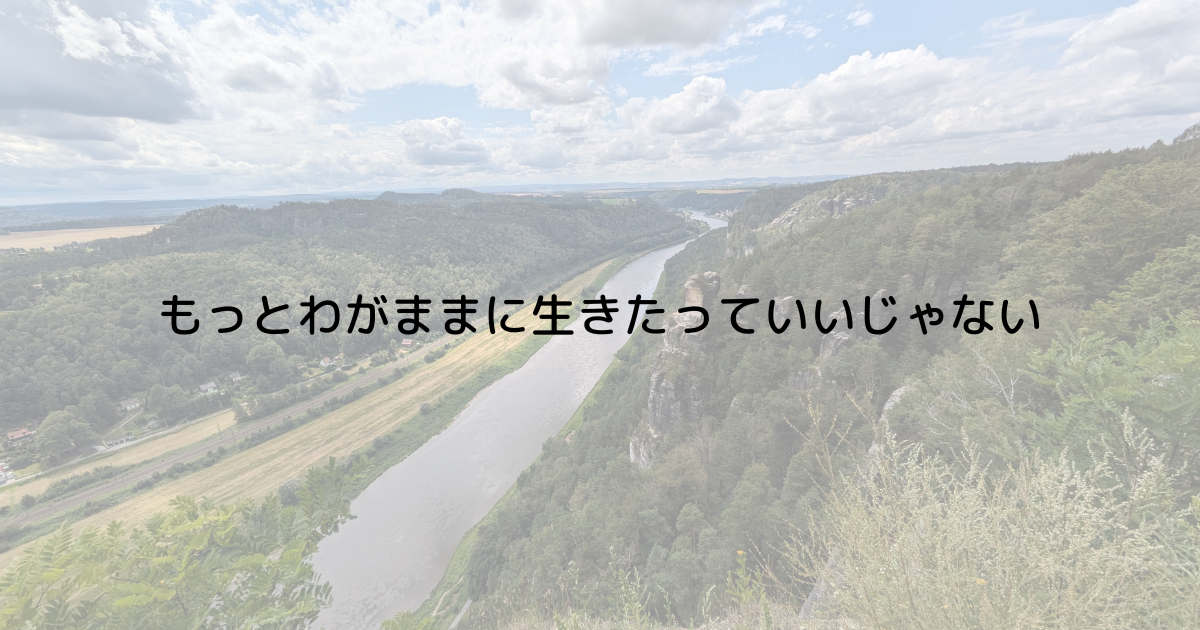みなさんこんにちは。
最近ようやく夏らしい陽気になりつつある、
かと思えば朝晩寒かったりとなかなか落ち着かない
ライプツィヒである。
いかがお過ごしだろうか。
先日、学校のイベントで「ザクセン・スイス国立公園」に行ってきた。
ドイツ人の友人曰く、これは登山ではなく散歩だとか。その心持ちでそこを訪れたわたしは
度肝を抜かれた。登りは階段が続き、なかなか
ハードではあるがそれ以上に頂上の眺めは
素晴らしい。自然の雄大さとともに、時の流れを感じさせない絶景についついなにかも忘れて
しまうくらいの、ただぼーっとそこにいるだけでいい。と自らを肯定してくれる場所だと感じた。
誰もが釘付けになること間違いなしの光景に、
ドイツ人に愛される理由も納得だ。
特にこの夏の時期は天気が気持ちよく、一段と
オススメしたいところである。
「大人の心」という苦しみ
さて、前置きはそうと。今回は、あまりにも
「大人の心」という社会の常識で生きてきたわたしの
苦悩から、わがままに生きることを覚えたわたしの体験を綴りたいと思う。
ドイツに来るまで苦しかった、というかどこか居心地の悪さをずーっと感じていた。「社会の常識」
という箱に閉じ込められ、おりに入れられたしまった動物のように、わたしはそのなかをぐるぐる
周り続けていた。これまでに、こういうことを言われた経験はないだろうか。
「そんなに社会は甘いもんじゃない」「みんな自分が好きなことで生きていければみんなとっくに
幸せになっている」と。
そういう雑音を、わたしが最近読んだ本の「地平線を追いかけて満員電車を降りてみた」という作品
のなかで、「大人の心」と名付けている。
すこし話が脱線するが、このタイトルに非常に惹かれた。
わたしが思うにこのタイトル、地平線は本来自分のやりたいことや好きなことのたとえで、
満員電車とは、いまそのひとがどこか違和感を感じながら働いているようすを表しているのではないかと思う。
そういう日常の違和感を脱すべく、満を持してその舞台から飛び降り、自分の好きなことを追いかけているよう。
ぜひ、みんなにおすすめしたい本の1冊だ。この本のなかで、それぞれの悩みを抱えたたくさんの主人公が
登場するのだが、まさに自分も同じような悩みを抱えていたからこそ、読んでいて
とても心が痛くなる。
さて、「大人の心」というのは、まさに自分たちに直結する苦しみの中心にあるものだとわたしは思う。
社会の地位や名誉のために、他者からの評価を得たいがために自分の心とは相対する行動を取ってしまう。
それを手に入れられるうちはいいが、その舞台で勝ち続けるのには必ず限界があるし、
自分の心は気づかないうちに疲弊している。
非常に生きづらい。
それが限界に達したとき、大人の心はまるで、これまでなんとか静止を保っていた天秤が途端に安定感を無くし
片方に偏ってしまうように。
「子どもの心」を忘れてはいけない
だからこそ、「子どもの心」を忘れてはならないと強く言いたい。
ここでいう子どもの心とは、まさに大人の心とは真逆の心の状態だ。自分の心が思うがままに周りを
気にすることなく、今は遊びたいから遊ぶ。この心は、大人の心が数字や物など見える形で判断する
のに比べ、目に見えるものがほとんどない。だからつい、この心は軽視されがちでわたしもそうだった。
例えば、子どもが砂場でお城を作っている場面で、それなんのために作っているの?とはならないだろう。
その子はただただ、いまそれがやりたいから、自分の心に素直に従いそれを行動に移しているだけ。
大人の心で完全に覆いかぶさられた子どもの心を思い出すことこそ重要な気がする。
真正面から我の心に向かい合い、いま自分が求めるものはなにか、1mmでも自分の心が震えるものはなんなのか、
自分に自分で聴いてみることは最も大切な作業かもしれない。
そうして、少しずつ自分自身にわがままになっていくことが、自分の心を満たす一番の近道だし、
大人の心という幾重にも絡まった鎖から放たれる方法だとわたしは思う。
みんなの応援団長でいたい
わたしは、このブログをご覧の通り日本人に向けて発信しているわけだが、特にいま日本で生きる若年層に向けて
発信したいと思って書いている。
わたしもまだまだ道半ばではあるが、わたしも自分の心が動いた、ドイツはライプツィヒに降り立ち、
そこでいまは我ら鹿児島が誇るそしてわたし自身もこよなく愛する、「芋焼酎」をライプツィヒで展開し、
ひいてはヨーロッパで日本酒と同じくらいの地位を築き上げたいと思っている。
(最初は歌を学びたいと思ってライプツィヒに来たが、生活するうちに焼酎に自分の心が向いたため
そちらに素直に従ってみた)
そしてひいては、よく日本で言われる「好きなことで食べていくのはムリ」という社会のステッカーを
きれいに剥がしたいし、それがムリではない!ということを自身の体験から証明したい!
さらには、それは若年層にいまの環境を見つめるきっかけや、勇気のいる一歩を踏み出す後押しになってくれたら、
これほどうれしいことはないと思うところで、今回の投稿を終えたい。
書きたいことが多すぎて、これだけの量になってしまったが、ここまで読んでくれてありがとう。
そして、最後にわたしは自分の実体験を通し、「みんなの応援団長でありたい」とかなり強く思う。
感想や質問などあれば、お問合せページからお願いします。
それではまた。