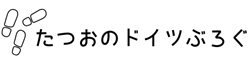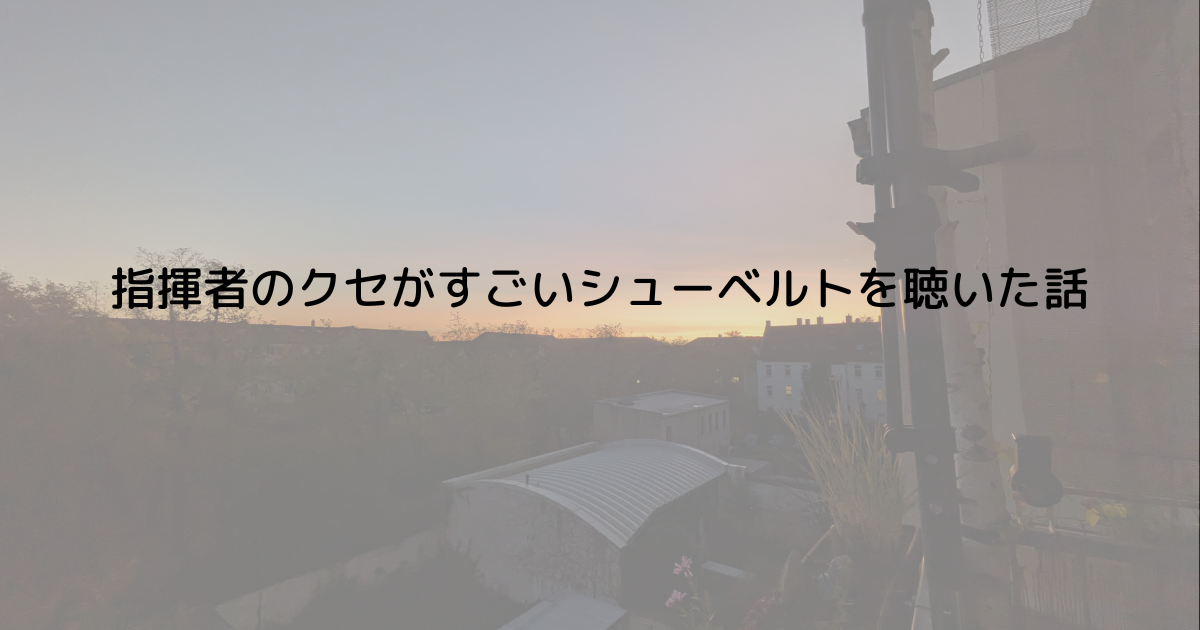みなさんおはこんにちは。いかがお過ごしだろうか。
つい数週間前、みなさんご存知の衆議院選挙の開票日であった。また別の記事で紹介したいが、
ライプツィヒで月末の土日にとにかく壮大なフリーマーケットが行われている。日曜日にそのフリーマーケットに行きたくて行ったものの、
選挙の結果が気になり落ち着いて掘り出し物を見つけられないと、早々に切り上げてしまった。
こんなに選挙結果が気になる自分にも驚きだったが、選挙結果にも驚きだった。結局はなんやかんやいって、
自民・公明党あわせて過半数いくのだろうなと予想していたからだ。
これから石破首相は、どのように政権を
運営していくのか注目したいところである。
《ザ・グレイト》を通して見える世界
さて前置きは短くして、先日シューベルト作曲「交響曲第8番 ザ・グレード」をゲヴァント
ハウスオーケストラの演奏で聴いた。
指揮者はゲヴァントの常任指揮者であるアンドリス・ネルソンス氏ではなく、ゲストのフランツ・ウェルザー=メストという指揮者だった。この演奏個人的に、すこし期待外れの演奏であったためその詳細のようすをお届けしたい。また、シューベルトの交響曲にはちょっとややこしい歴史があったことを
知った。そちらもあわせてお届けしたいと思う。
8番なのか9番なのか分からない
シューベルトの8番はわたしの大好きな作品の
ひとつだ。それこそ、ドイツに来る前からYouTubeなどで
たびたび見聴きしており、いつかは生で聴きたいと思っていた。わたしはいつも、コンサート前には決まって、YouTube Musikで
その曲をわりと念入りに聴いて、本番に
臨む。今回は、8番をゲヴァントハウスの演奏、
ヘルベルト・ブロムシュテットの指揮で
聴いた。
聴いていて、一定の安定感があり引っかかることなく最後まで聴け、なによりCDを聴いていても彼の指揮を
振っている姿が、目の前に浮かぶのだ。ここで、このCDのタイトルを
見ていて違和感を覚えた。
このCDのタイトルは、Schubert「交響第9番 ハ長調 D944《ザ・グレイト》」のなのだ。今回わたしが聴きに
行ったプログラムを見てみると、Schubert「交響曲8番 ハ長調 D944《ザ・グレイト》」(分かりやすくするために本来ドイツ語表記のところを日本語表記にしている)なのだ。お気づきだろうか。交響曲のあとにきている
番号を除いては、同じタイトルだ。この違いにわたしは驚きと同時に戸惑いを覚えた。
まさかゲヴァントハウスに至っては、プログラム表記を間違えるなんてことないよな。はたまた、わたしが聴いたCDの発行元ドイツ・
グラモフォンが間違えるとも考えにくい。どういうことなのか分からないうえ、ここにはややこしい生い立ちが
あったことを、この時点でわたしは知る由もなかった。
《ザ・グレイト》いまでは8番に
さっそくわたしは、この疑問を解決するべくGoogle先生に助けを求めた。そうすると、やはりたくさんのひとがわたしと同じ疑問を抱いていたのだろう、多くのウェブページがヒットした。
そのなかでこちらのページを参考にさせてもらった。
この曲は世界的に知られるようになり、自然と「第七番」の交響曲として番号が付けられました。
ところがその後、さらに未発表の交響曲が発見されます。これは2楽章までしか書かれていなかった
ため、交響曲「未完成」として発表されました。4楽章で構成されるべき交響曲の形式としては未完成
ですが、あまりに素晴らしい曲で、精神的には完全に完成されています。この「未完成」交響曲は
「第八番」とされましたが、後になって第七番交響曲より以前に書かれた曲であることが判明し、
番号の入れ替えがありました。さらに、まだまだ膨大な未整理の楽譜が残っていたため、オーストリアの音楽学者オットー・
エーリヒ・ドイチュによって事細かな調査が行われ、作品番号の整理が行われました。そこで発見されたホ長調の交響曲が、作曲年代に従って「第七番」として食い込みます。それがシューベルト作品
番号の基本として受け継がれてきました。私もこれに従って、「未完成」が第八番、「ザ・グレート」が第九番と思って長年親しんできました。ところが、2007年のシューベルト没150周年を機に、国際シューベルト協会によって再び作品番号の整理が敢行されました。その結果、第七番交響曲は自筆譜では演奏不可能との理由から外され、
再び「未完成」交響曲が第七番、「ザ・グレート」が第八番へと変更。
やれやれ、私の頭の中もいまだに整理がついていません。
こんな入り組んだ歴史があったことをみなご存知だっただろうか。簡単に要約すると下記の通り。
わたしがコンサート前に聴いたCDは、わたしの
勝手な想像に過ぎないがおそらく、最終的に国際シューベルト
協会によって番号が統一される以前に商品化されたものなのだろう。
そのため、同じ曲でありながら番号が
異なるのだなと自分のなかで納得した。
残念ながらも最後には…
この《ザ・グレイト》は、シューベルト死去後シューマンによって発見され、メンデルゾーン指揮ゲヴァントハウスオーケストラにて初演されたのだ。それを事前情報と頭にインプットしていたものだから、このコンサートに対する期待はとても大きかった。しかし、今回聴いた演奏はわたしの期待のはるか斜めをいっていた。
あまりマイナスなことは書きたくないのだが、ここでは
正直な気持ちを遺しておきたいと思う。
この指揮者は
ほんとうに指揮をしているんだろうかとちょっと疑わしいところがあった。後ろから見れば、指揮台の上で
突っ立っているようにも見えたのだ。決めつけは、第三楽章の曲調が変わるところで、ジェットコースターが
急上昇するイメージの違和感を覚える音が入ってくる。
さらには、わたしがいちばんの聴きどころだと思う
ところでは、すこし退屈でちょっともたついた感じがあった。ただ、それに逆らうようにソロを弾くオーボエや
フルート、クラリネットなどは、それぞれにうっとりした美しさがあった。この世界感がずっと続けばいいのにと懇願したくなるような。だから結局最後は、なんやかんやよかったよねという印象に落ち着くのだ。
おわりに
すこし批判的なことを言ってしまったが、
クラシックの本場ドイツにいると、こういう歴史的な瞬間には当たり前のように立ち会える環境がある。《ザ・グレイト》が初演されたその地でそのオケで聴くという貴重な音楽体験だけで心が震えるものだ。そういえば、数か月前ライプツィヒ市立図書館でモーツァルトの新曲が見つかった。見つかった数日後には、早くもここライプツィヒで初演され、そこからさらに数日後には、元々プログラムには入っていなかったゲヴァントハウスのプログラムにも入れられ演奏された。
モーツァルトのこれまでの作品集に新曲が追加されたのだ。
昨日は、いまのゲヴァントハウスの礎を築いた、メンデルスゾーンの177年目の命日だ。
ライプツィヒでは
いままさに、「メンデルスゾーン音楽祭」が開催され、連日メンデルスゾーンの作品が街中で演奏されている。
わたしも連日コンサートに出かけている。大好きな街で大好きなオーケストラを聴きに行く。それはわたしが
心を緩められる瞬間でもある。そういう瞬間を大切にしたいし、そう感じられる自分の心をしっかりと受け止めている。人間はたくさんのひととかかわりあうことで、自分の存在価値を認識したり、喜びや悲しみを共有し
あったりしている。ただ、そこには他者から受ける何かしらの攻撃や気分を害することが何かしらあるはず。
だからこそ、自分のなかで気を緩められる瞬間があることは、すごく大切なことだと思う。いまそういう瞬間がないのであれば、ぜひ意識的に作ってみることをおすすめしたい。
今日も最後まで読んでくれてありがとう。
次回の投稿もお楽しみに。お問い合わせなどは以下のボタンからどうぞ